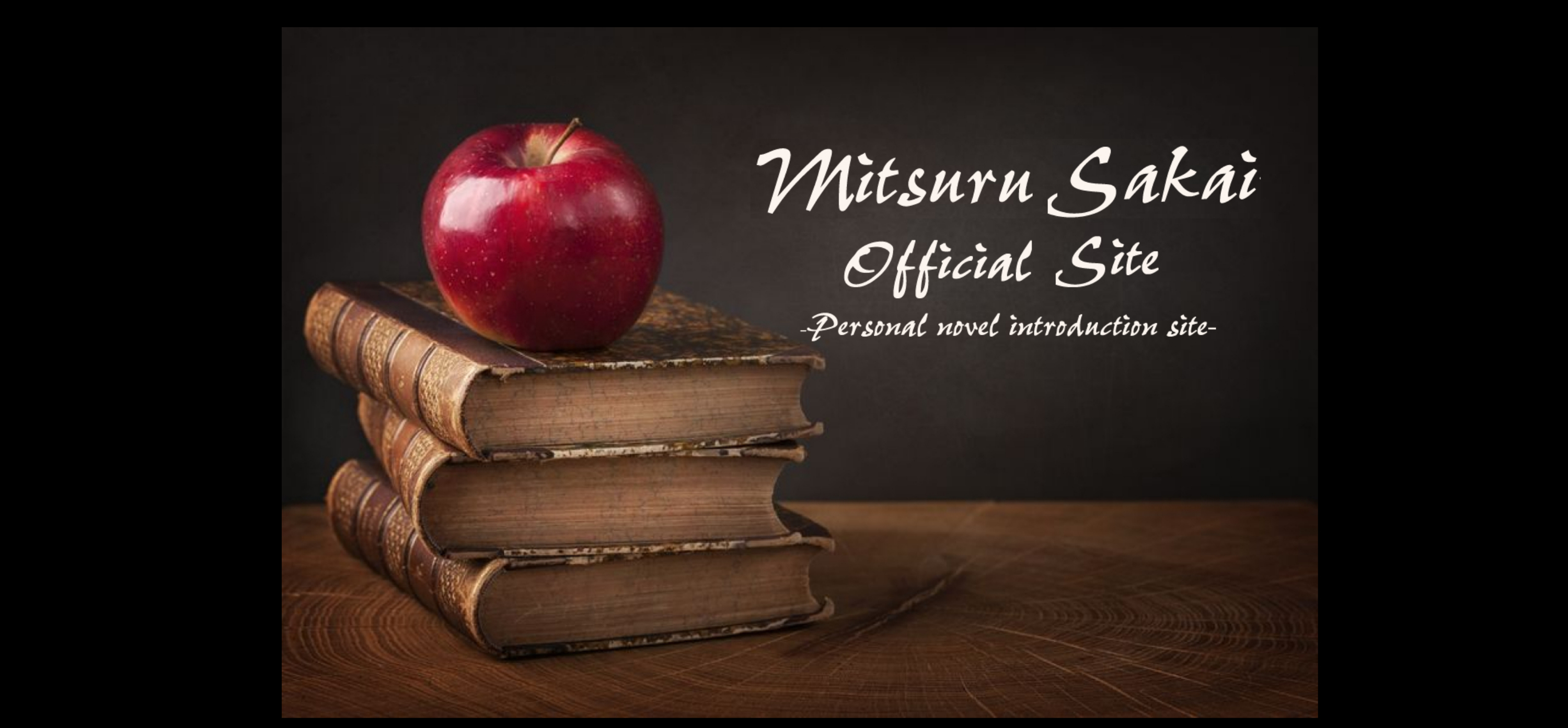創作の台詞でお馴染み『わし』とか『○○じゃのう』とかって老人語はどこから来たの? その起源は?
- 2021.06.05
- 事実は小説よりも奇なり

どうも、さかいです!
実は前々から個人的に不思議に思っていたことがありまして。
皆さんは疑問に感じたことはないですか?
よくフィクションなんかで、お年寄りのキャラクターが一人称を『わし』と呼んでみたり、語尾に『じゃのう』とか言ってみたり。
こういった言葉使いって現実では、あまり耳にすることって少ないと思います。^^;
というより聞いたことない。(爆)
※ちなみに自分の場合は、小説内で台詞に用いる際、こういった言葉使いは嘘臭く聞こえるので嫌う傾向にあったりします。^^;
で、少し調べてみました。
何故、お年寄りの登場人物たちが、こういった話し方をするようになったのか。
その起源について。
『老人語』の起源

よく漫画やアニメ、SF小説等の作品内では、高齢であることがストーリー上、重要な意味を持つ登場人物の言葉づかいに、一人称「わし」や語尾「じゃ」、打消し「ぬ(ん)」といった特定の言い回しが、しばしば用いられます。
実は、このような所謂「老人語」は、江戸時代の上方語が起源なのだそう。
18世紀後半以降、セリフの約束事として、老人や知識人を表現するための役割語として芝居や戯作等の世界で使われだしたのを機に、それが明治時代以降、小説や漫画などにも広まり定着したものなのだとか。
なんでも江戸時代中頃より、東国的な表現を基本とする江戸語が新しい共通語として形成されます。
若年層がこれを自分達の言葉としたのに対し、高齢者層、特に知識人層には、依然として上方風の保守的な言葉を使う人々が多かったのだとか。
現代で例えると『エモい』とか『辛み』とか言ったりするような感じですかね?(笑)
このような高齢者の話し方は、歌舞伎や戯作、落語、講談等の中で誇張して描かれ、次第に「老人語」として定着していきます。
その伝統は近代以降、少年雑誌や漫画に受け継がれることに。
なかでも手塚治虫の強い影響によって、高齢の博士等の台詞に老人語が多用されるようになっていきます。

さてさて、いかがだったでしょうか?
その起源は江戸時代。
普及させていったのは、我らが日本の誇る漫画の神様、手塚治虫さんだったなんて少し意外でしたよね。
なんだか台詞回しとしては少し白々しく聞こえてしまう反面、こういった『老人語』は、たったの一言で読者や視聴者に『あ、この人は老人なんだな』と思わせてしまう説得力があります。
そういったメリットが、所謂、創作の中で普及していった理由のひとつとも言えるでしょう。
あなたは、どう感じましたか?^^
参考文献:Wikipedia
-
前の記事

S.H.Figuarts(真骨彫製法) シャドームーンが発売されるみたいだけど 2021.06.04
-
次の記事

【近況】次回作なんかについて。行き過ぎたエロ描写にブレーキをかける! 2021.06.06