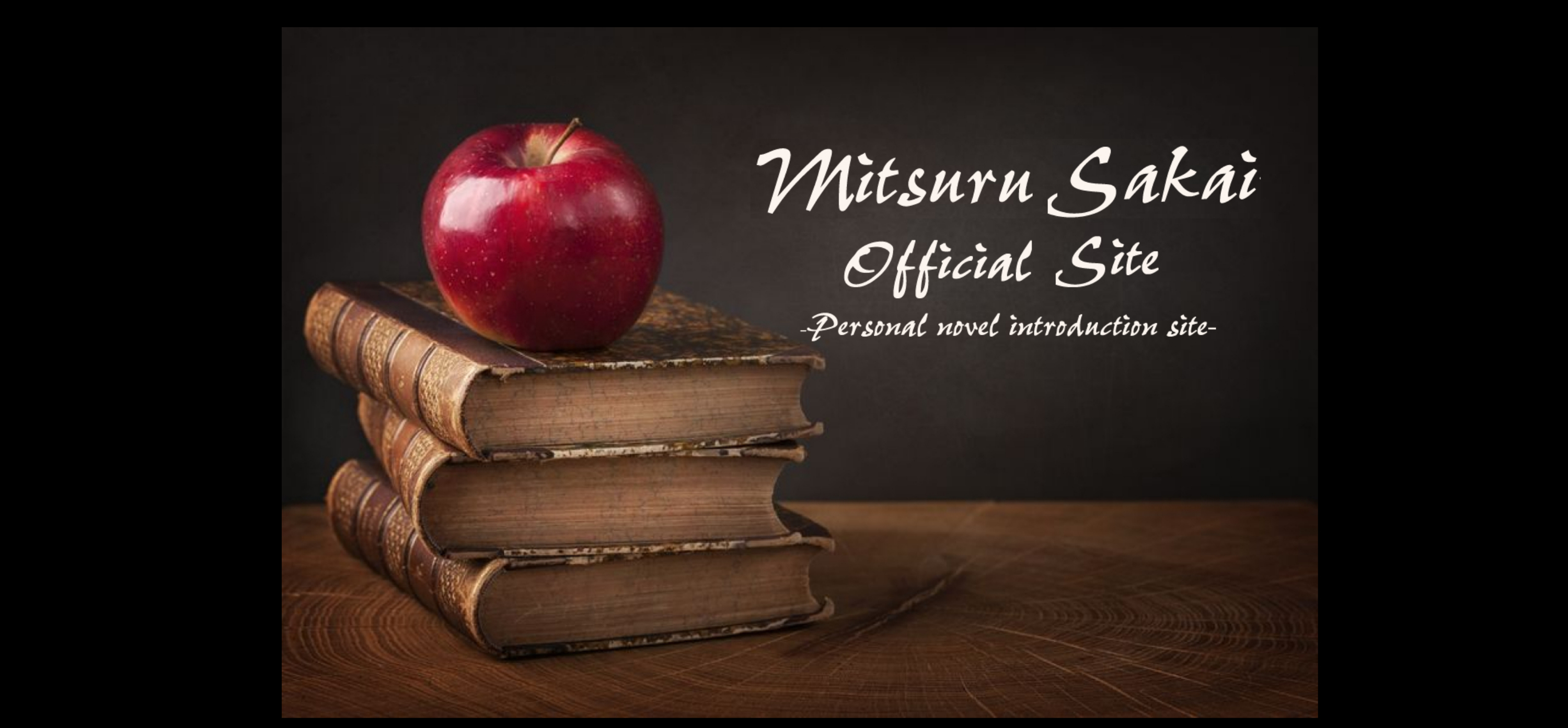そもそも民間軍事会社(PMC)って何? どんな組織?
- 2022.10.16
- 事実は小説よりも奇なり

どうも、さかいです!
皆さんは民間軍事会社をご存知でしょうか?
近年ではアニメや漫画なんかの影響によって、一度は耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか?
そんな今や、あらゆるコンテンツに登場するようになった民間軍事会社とは?
そもそも、どういった組織なのか。
今回は、その実態について迫っていきたいと思います。
概要

民間軍事会社(みんかんぐんじがいしゃ)とは、直接戦闘、要人警護や施設、車列などの警備、軍事教育、兵站などの軍事的サービスを行う企業。
PMC(private military company または private military contractor)、PMF(private military firm)、PSC(private security company または private security contractor)などと様々な略称で呼ばれます。
だが、2008年9月17日にスイス・モントルーで採択されたモントルー文書で規定されたPMSC(private military and security company、複数形はPMSCs) が公的な略称です。
民間軍事会社は1980年代後半から1990年代にかけて誕生し、2000年代の「対テロ戦争」で急成長します。
国家を顧客とし、人員を派遣、正規軍の業務を代行したり、支援したりする企業であることから、新手の軍需産業と定義されつつあります。
例えとして適当かどうかはわかりませんが、派遣会社の軍隊版として捉えていただいて遜色ないでしょう。
主な業務としては
・軍隊や特定の武装勢力・組織・国に対して武装した社員を派遣しての警備・戦闘業務
・武装勢力に拘束された人質の救出
・窮地に陥った要人の逃亡支援など救助・救援業務、兵站・整備・訓練等の後方支援
などなど。
戦闘一辺倒だった旧来型の傭兵と異なり提供するサービスは多岐に渡ります。
民間軍事会社と聞くと、どうしても戦闘行為ばかりをイメージしがちですが、人道的な支援も業務に含まれます。
・近年、軍の増派がたびたび政治問題化していること。
・より多くの正規兵を最前線に送るために後方支援や警備活動の民間委託が進んだこと。
・政治的理由などで特定の国の軍隊が活動しにくい地域でも、民間企業なら自由に行動できる。
・民間軍事会社の社員の死者は公式な戦死者に含まれない。
などの理由から、その活用が進んでいます。
少し言葉は悪いですが、まさに使い捨ての消耗品。
映画『エクスペンダブルズ』を彷彿とさせます。
イラクやアフガニスタンでは、従来であれば正規軍の二線級部隊が行ってきた警備や兵站、情報収集など後方業務を外注する民間組織として正規軍の後方を支える役目を担い、多い時で約26万人の民間人が米国政府の業務に関わったとされます。
その一方で軍人、民間人、傭兵のどれにも当てはまらない曖昧な存在であること。
需要が増大し急速に規模が拡大したため、管理が行き届かず多くの不祥事を起こした事などが問題になってます。
その一例を挙げます。(あくまで現時点で明るみに出ている事件です)
2004年3月
ファルージャの戦闘

PMSCsコントラクターが民衆に惨殺され、町を引きずり回された後に焼却、橋に吊るされるという事件が発生。
これが原因となりファルージャで多国籍軍と武装勢力が軍事衝突。
4月と11月の戦闘を合わせて多国籍軍側100人以上、武装勢力と民間人にそれぞれ1000人以上の死者が出た。
2007年9月
ブラックウォーター事件

バグダッドにおいてブラックウォーターの社員がイラク人17人を射殺する事件が発生。
当初ブラックウォーター側は正当性を主張したが、アメリカ政府は、少なくとも14人の射殺には正当性が認められないと判断した。
一方で、アメリカ政府はブラックウォーター社との再契約を「問題ない」とし、その契約を継続している。
2019年末
カルロス・ゴーンの国外逃亡を支援

日本において保釈中だったカルロス・ゴーンの国外逃亡を支援。
元グリーンベレー隊員のマイケル・テイラーが事件に関与していました。
テイラーは、American international security Corp (AISC)という民間軍事会社の代表でもありました。
これらのように報酬次第で明白な違法行為も辞さない輩が一定数、存在します。
2008年9月、スイスの国際会議においてアメリカや欧州諸国、中国、イラク、アフガニスタンなど17カ国は民間軍事会社に国際法を順守させるため、各国に対して適切な監督・免許制度の導入、採用時の審査の厳格化、戦時の民間人保護を規定した国際人道法や人権法に関する社員教育の強化など適切な監督を求める具体的な指針を盛り込んだモントルー文書を採択しました。
名称について

日本では民間軍事会社、民間軍事請負企業などと呼称されます。
民間軍事会社を示す英語での正式な名称が決まったのは2008年9月17日にスイス・モントルーで採択されたモントルー文書でPMSC(private military and security company)(およびその複数形のPMSCs (companies))の略語が使用されてから。
正式名称が決定される前は、民間軍事会社について報道機関や文献によって異なる名称が使用されており、PMC(private military company または private military contractor)、PMF(private military firms)とさまざまだったが、モントルー指針にならいアメリカ国防総省や民間軍事会社の管理組織であるIPOAやBAPSCもPMSCの語を使用していることから、現在ではPMSCが正式名称となってます。
国際政治学者のP・W・シンガーは『戦争請負会社』でPMFと表記してます。
歴史

第二次世界大戦後には各国で法が整備され会社軍のような存在は規制がかかり、治安が不安定な地域で操業する鉱山や油田の警備に支障を来すようになります。
そこで警備会社という名目で設立。
かつて会社軍が担当していた軍事サービスを他の企業に提供する会社が登場します。
民間企業でも自社で直接雇用するのに比べ、必要なときに必要な数の人員を確保できるためメリットは大きいものでした。
(この辺りは現在の派遣会社のビジネススタイルにも似てますね)
1991年のソビエト連邦の崩壊に伴う冷戦の終結により、アメリカ合衆国を中心とした各国は肥大化した軍事費と兵員の削減を開始。
その際、数多くの退役軍人を生み出します。
冷戦終結以降の世界では超大国同士がぶつかりあう大規模な戦闘の可能性は大幅に少なくなったものの、テロリズムや小国における内戦、民族紛争など小規模な戦闘や特定の敵国が断定できない非対称戦争が頻発化、不安定な地域で行動する民間人を護衛する需要も増加します。
優秀な軍歴保持者は有り余り、軍事予算の大幅な削減に伴い軍隊のコスト面での効率化が求められ、そして小規模の紛争が頻発。
こうして特定の国家に属さない「国境の無い軍事組織」として立ち上げられることに。
その後は民間軍事会社の元祖とも言える「エグゼクティブ・アウトカムズ」が誕生し、既存の軍関連会社も次々と民間軍事会社化していくことになります。
人員数

1991年の湾岸戦争時には全兵士における民間軍事会社従業員の比率は100:1と言われてましたが、2003年のイラク戦争時はおよそ10:1と言われています。
イラクに駐留する民間軍事会社の人員は、一説にはアメリカ人が3千人~5千人。
イギリスなどのヨーロッパ人や南アフリカ人では7千人から1万人。
貧困国の出身者では1万5千人から2万人。
イラク現地で雇用された者が2万5千人から3万人。
だと言われています。
また、受注した会社がさらに他の会社に仕事を丸投げしたり再発注しており、イラクに駐留する民間軍事会社の正確な社員数を把握する事の障害にもなっているようです。
1994年のルワンダ紛争においてはエグゼクティブ・アウトカムズ社はいつでも1500人規模の部隊を展開出来る準備を整えていました。(結局、実行はされず)
これはアフガニスタン侵攻時のアメリカ海兵隊の先行侵攻部隊と同規模だったようです。
経歴

アメリカ人やイギリス人など欧米圏の社員を雇用する際には、正規軍の兵士経験者(特にデルタフォースやDEVGRUといった有名特殊部隊に所属する元兵士を優遇する)を雇用することが主体ですが、社内の基準を満たしていれば(厳格な選抜試験を受けさせる会社もあれば、契約書にサインすれば誰でも入れる会社もある)、警察官や軍隊経験のない一般市民を雇用することもあります。
先進国の人員だけを雇用して警備などをしては、限られた人件費が高騰することや素早く効率的に人材を供給できないという事情から、フィジー、ネパール、フィリピン、コロンビアなどの、近年まで内戦や紛争状態にあり、実戦経験者が豊富な貧困国から元兵士が送られている割合が多いようです。
アメリカのブラックウォーター社においては貧困国の出身者が警備要員の4割、「トリプル・キャノピー社」に至っては8割を占めてます。
トリプル・キャノピー社は設立当初実態のない会社でありながらも大型契約を取得し、チリ人やフィジー人と少数のアメリカ人を雇って、イラク全土にある13ヶ所の連合暫定施政当局に1000人もの警備員を派遣しました。
また、イラク現地では多くのイラク人が雇用されています。
G4S社の場合は英国人2名にイラク人6人で身辺警護小隊を編成しており、欧米人の将校下士官に現地人の兵士という構成が取られています。
このような雇用方式は「エリニュス社」や「アーマー・グループ」など、他の英国系民間軍事会社でも用いられる方針です。
イラク人は警備員だけではなく、空港の荷物チェック係といった非戦闘員としても雇用されてます。
リクルートに関しては、ピンからキリまでが実態であり、貧困国の新聞に警備要員と称して募集広告をかけ、戦場に送り込むといった粗っぽい手口を講じる会社も存在します。
報酬

元有名特殊部隊所属の肩書きを持つ人材は1日で1000ドル程度の収入を見込めますが、ネパールのグルカ兵が民間軍事会社で働いた場合の給料は月給1000ドル程度。
ただ、ネパールの公務員の平均年収が1300ドルであることから考えると月給1000ドルという給料は彼らの所得水準から見ると大変に高額。
このため、貧困国の兵士にとっては民間軍事会社のコントラクターになって得る給料は普通に働く場合の10倍以上にもなり、一攫千金を夢見るに十分な額といえます。
どうやら出自や経歴、その国の物価によって報酬の額も増減するといったところなのでしょう。
逆に日本などの先進国の国民から見れば一般企業の賃金と大差の無い、もしくはそれ以下の給与水準であり、危険性に比して薄給で、日本人が民間軍事会社で就労しても大金を稼げるとはいえない。
普通にバイトで稼いだ額と、いつ命を落としてしまうかもわからない環境下で稼いだ額が同じとか嫌すぎます。^^;
実際にイラクで死亡した日本人コントラクターの年収は四百数十万円程度なのだとか。
軍歴が長く下士官であったことから考えれば先進国の正規軍と変わらない報酬です。
このため、民間軍事会社の給与は裕福な先進国の国民から見れば安く、貧困国の国民から見れば高給ということになっているというのが現状。
また、軍隊と比べると遺族補償、軍人恩給、褒賞といった福利厚生面は手薄だったり制度自体がない事も多い。
如何に体よく扱われているかが透けて見える事例ともいえますね。
なお、民間軍事会社においても兵士は兵士、下士官は下士官で終わりという点に(多少の例外はあるものの)変化はなく、たとえ入社前に歴戦の勇士でも、入社後にどれだけ実績を重ねても、入社前に幕僚課程や上級士官課程を取得していない者は現場指揮官以上に昇進できないとされています。
うーん、世知辛い。><
まるで漫画!? なかには強大な軍事力を誇る企業も?

小国なみの軍事力を有する民間軍事会社。
そんな漫画みたいな設定の企業が存在したとしたら?
皆さんは、どうしますか?w(別にどーもしねーよw)
冷戦末期の1989年に南アフリカで設立されたエグゼクティブ・アウトカムズ社が代表格。
その実績も目覚ましく。
アフリカのアンゴラやシエラレオネの内戦で政府と契約するや、圧倒的な軍事力で反政府組織を鎮圧したのだとか。
その装備も凄まじいものでした。
ソ連の崩壊で余剰兵器として横流しされたと思しき銃火器、戦車や装甲車、攻撃ヘリから戦闘機まで多数保有。
ソ連崩壊後、武器管理の杜撰さは有名ですね。^^;
そんな冷戦終結後の負の遺産ともいえるエグゼクティブ・アウトカムズ社でしたが、そのあまりの強大な軍事力で介入するため契約した政府の方が国際的非難を浴びせられるハメに。
結果、1998年に南アフリカ政府から非合法化、解体されてしまいました。
まだ、民間軍事会社も過渡期。
その認知度も薄く、かつ凡例や事例も少なかったため好き放題やれていたというわけですね。
勿論、このようなやり方は近年では通用しません。
立場が逆転? 軍が指導を受ける時代

あくまで現代の民間軍事会社は警備会社という位置づけ。
世論から戦力として見られないようクリーンなイメージ作りに徹しているというのが現状です。
表向きは、戦争を行うのは国家に忠誠を誓った軍隊と軍人であり、民間軍事企業はその活動を手助けするにすぎない。
というのが大義名分です。
そのため、戦場にならない地域の警備員だったり、訓練に対するコンサルタント、オブザーバー的な役割に徹する機会が多くなってきています。
また、高度な訓練や教育を受けた退役軍人が多いことから、そうした兵員の育成ができない貧困国で重宝されそうなイメージもありますが、近年ではむしろ先進国での需要も増えてきてます。
なんと、その最たる例がアメリカ。(意外ですね)
戦闘機も含む退役した軍用機に、退役した軍人が乗って訓練の時に敵機役を演じたり。
各種の訓練支援プログラムを提供する民間軍事会社と常に契約しており、日本の米軍基地でも民間登録の軍用機が活動しています。
百戦錬磨の経験を持つ歴戦の英雄から直接、ノウハウや訓練を受けられるなら、まさに願ったり叶ったり。
互いにウィンウィンというわけです。
プーチンの隠密部隊『ワグネル』とは?

公式にはその存在すら否定されている、ある傭兵部隊。
彼らは世界各地で市民の殺害など残虐な行為にかかわったと指摘されています。
金で傭兵を雇い、戦場へ送り込む民間軍事会社「ワグネル」。
ワグナー・グループ、またはワグネル・グループは、ロシアの準軍事組織です。
ロシア大統領府は否定しているものの、「ワグネル」はプーチン大統領とも関係が深いとされ、ウクライナだけでなくこれまで中東のシリア、アフリカなどで動きが伝えられてきました。
近年、かつてワグネルに所属していた元メンバーによるインタビューが物議を醸しています。
取材に応じたガビドゥリン氏は「ワグネルとロシア政府はつながっている」と証言。
闇に包まれた“よう兵集団”を使い、ロシアがひそかに進める戦略。
その一端が明らかになって来ています。
どこまで戦力として通用する?

先述した通り民間軍事会社は、あくまで民間の企業。
表向きは戦争の道具ではありません。
そのうえで少し考えてみたいと思います。
有事において民間軍事会社は、どこまで戦力として通用するのか?
確かに組織には華々しいまでの実戦経験、豊富なノウハウを有した猛者が所属しているかも知れません。
しかし、如何に多くの実戦経験を積んだ猛者であろうと、あくまでも彼らは雇われ集団に過ぎず、それ以上でも以下でもない。
その精神は国家に忠誠を誓った正規雇用の兵士とは程遠い。
大義は勿論、別に守りたい国や家族があるわけでもない。
欲しいのは報酬。
目的は金であり生きていくための手段のひとつに過ぎない。
つまり、そこには大義も正義もない。
間違っても自分の命を犠牲にしてでも前線を死守する、などといった発想は生まれないし至らないはず。
そのことから、その士気においても雲泥の差といえるのではないでしょうか。
内戦なり戦争なり。
戦闘において士気は戦局を大きく左右します。
どんなに優れた兵器や人材を有していたとしても、士気がなければ効率的に取り回すことは不可能でしょう。
それは近年のウクライナ事情をみていても明らかです。
故に所属する側の戦況に応じて簡単に身を退いたり、場合によっては敵側に寝返ったりしてしまうことだってあるかも知れません。
味方側の情報を売ってみたり。
まさに命あっての物種。
誰だって金儲けだけのために命を落とすなんて御免ですからね。
窮地に陥った際、普通なら何億、積まれたって割に合わないと考えるはず。(なかには例外もあるかもですが)
もし自分が民間軍事会社に所属する社員だったら?
そう考えてみれば容易に想像がつくというもの。w
そのため純粋な戦力としては役不足。
あまり過信できない。
そういえるのではないでしょうか。
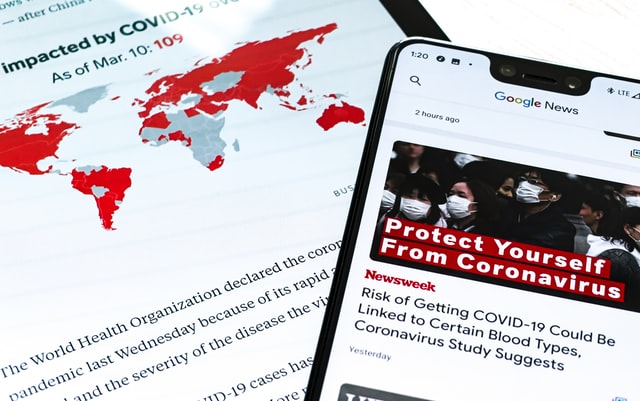
さてさて、いかがだったでしょうか?
どの国にも属さない独立した軍隊、民間軍事会社。
まるで漫画やゲームにでも出てきそうな設定ですよね。
しかし、そんな荒唐無稽とも思える私兵集団は確実に存在します。
表向きは単なる警備会社を謳ってはいるものの、その裏側に至っては殆ど知られていません。
仮にそこに何かしら政治的意図が働いていたり、非人道的な行為に荷担していたとしても何ら不思議はありません。
そのことは過去の事例が物語っています。
平和利用と戦闘行為。
一見、相反する構図にも思えますが、その存在は表裏一体。
世界各国の軍備増強が謳われるようになった昨今、我々は彼らの今後の動向に注視していく必要があるのかも知れません。
Wikipediaより引用
-
前の記事

【告知】懲役警察 B side diary『ホーム・カミング』 Kindleにてリリース開始! 2022.10.13
-
次の記事

【漫画化奮闘記】デジタル時代に漫画を描くということ 2022.10.16